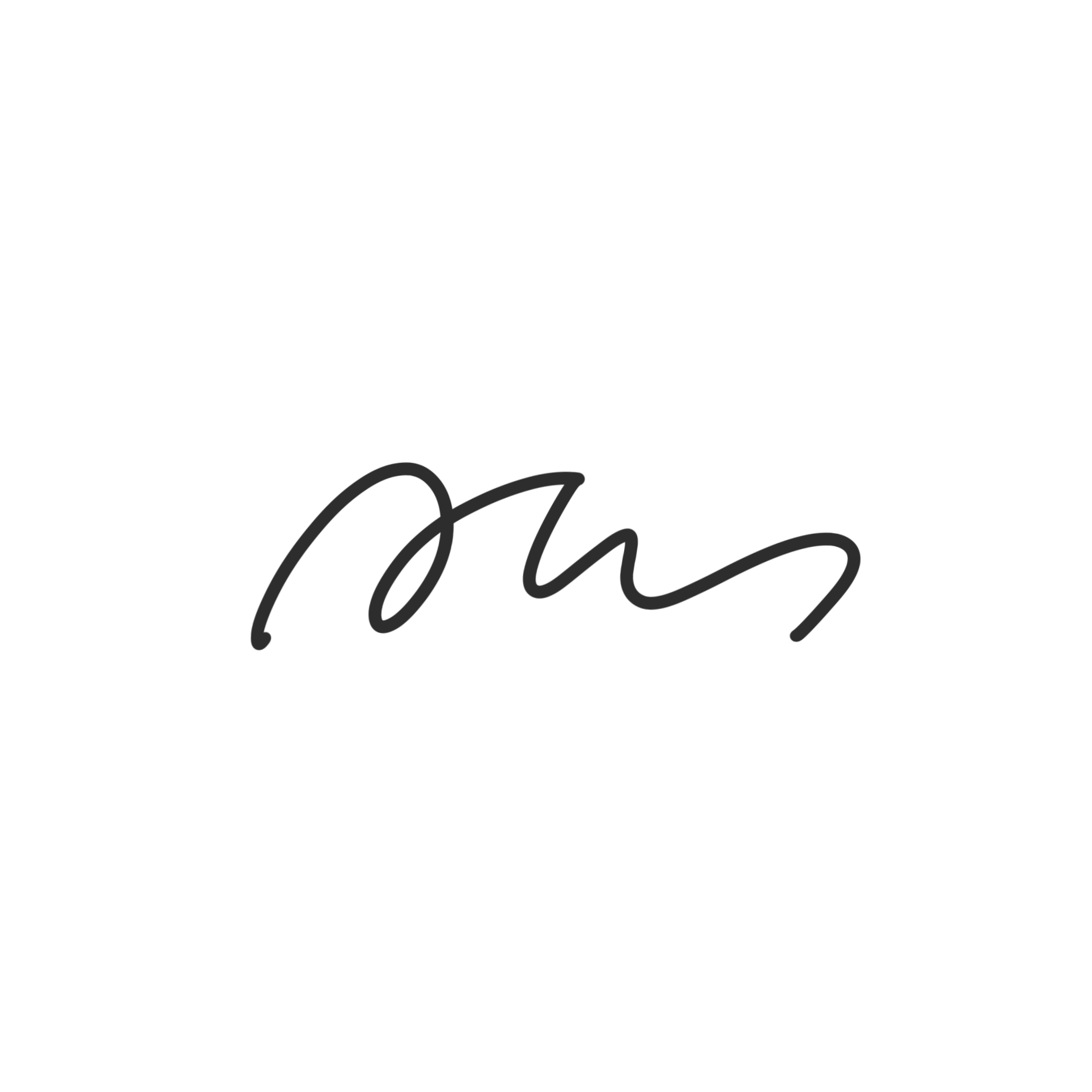「それじゃあ私はそろそろ帰ろうかな、お大事にね」
「うん、来てくれてありがとう」
「あ、そうだ!ちょっと早いけど、誕生日おめでとう!」
そう言って病室を出ていった彼女はハル。
歳は俺の2つ下の17歳だ。
幼少の頃家が近所だったこともあってよく一緒に学校に通ったりする仲だったが、お互いに段々と惹かれ合って、俺が中学を卒業する日に告白したんだったっけか。それから今日に至るまでずっと一緒にいるというわけで、まあなんというか、俺の一番大切な人というわけだ。
ああーーーー、普段と違う環境にいるせいか分からないが、柄にもなく甘酸っぱい思い出を引っ張り出してはこんな照れくさいことを考えている、そんな自分にふと気がついて一気に恥ずかしくなった。
ちょっとトイレに行くついでに涼しい空気にでも当たってこよう。
ううむ、それにしても松葉杖というのはどうにも慣れない、ちょっとした距離を歩くのも一苦労だ。前回入院したときは運良く病室のすぐ隣がトイレで便利だったのだが、今回は廊下の一番端と端。今どきの言葉に倣うなら「病室ガチャに外れた」とでも言うのだろうか。
そんなことを考えながら用も済んで自分の病室に戻ろうとしている途中、廊下の椅子に座っている少年が目に入った。服装や振る舞いを見る限り、ここに入院している感じではなさそうだ。おおかた誰かの付き添いで来たのだろう。
なんだかちょっと難しそうな顔をしていたので、気まぐれで声をかけた。
「おーい、君、どうかしたの?」
「んーーちょっと残念なことがあったんだ」
「何があったんだい?」
「駅の近くのパン屋さん、ずっと行きたいなって思ってたんだけど閉店しちゃったらしいんだ」
駅周辺のパン屋と言われて思い当たるのは1つしかない。あそこは高校のときの俺の担任が、定年を過ぎてから「実はずっと夢だった」と始めた小さな店だ。俺もときどき通っていたので閉店のことは当然知っていた。長い間この街に愛されてきたが、もう彼も先が長くないということで店を畳んだらしい。
まあこんな話、わざわざこの少年に言うことではない。
「そっか、それは残念だったね。だけどあそこはけっこう昔からやってたのに、どうして1回も行かなかったんだ?」
「だって昔からやってるんだから、いつでも行けるって思うに決まってるでしょ?閉店するって知ってたらもっと早く買いに行ってたし、きっとたくさん通ってたよ」
「なるほどたしかに、それは君の言う通りかもしれないね」
さよならを言って少年と別れ、俺はその場を後にした。
ーー
病室に戻り、夕食を食べたり本を読んだりしているうちに気がつくとけっこうな時間が経っていた。消灯の時間はとっくに過ぎているが、今日ばかりは忘れてはいけない大事なやることがあるのだから早くに寝てしまうわけにはいかないのだ。
まもなく時計の短針と長針がまっすぐ縦に重なろうとしている。
ああ、年に一度のこの瞬間はいつもドキッとする、もう60回以上も経験しているはずなのに未だに慣れない。
そしてそれと同時に、この決して長くない人生の残量を大事に大事に使いながら生きようと、そう強く心に誓う瞬間でもある。
チッ、チッ、チッーーー
静かな病室に響く秒針の音を聞きながら、俺は目を瞑って手を合わせ、祈りを捧げる。
「ああ神様。私のこの1年間を、どうか、どうかよろしくお願いします」
…………
目を開けるとちょうど0時を回っている。
昨日まで15歳だった俺は今日、また1つ歳を取られて14歳になった。
aso